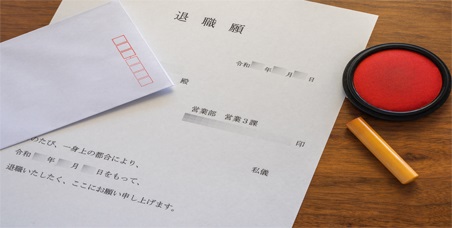2020/10/30
建築士・住宅設計士の転職で高収入やキャリア向上を目指す!役立つスキルと業界事情
建築士や住宅設計士は、堅調な住宅投資需要に支えられて売り手市場が続いてきました。活躍の選択肢も多く転職によって収入増やキャリアアップのチャンスもありますが、失敗しないためには転職動向を正しく知ることが大切です。本記事では、建築士や住宅設計士の方が転職の際に役立つ情報として、業界事情や活躍の分野、評価されるスキルや成功のポイントを紹介します。
建築士・住宅設計士の業界事情とは?需要と将来性
建築士や住宅設計士の方が転職を検討する際は、現在の需要や将来性など、業界を巡る動向を知っておくことが大切です。ここでは売り手市場の事情やその背景、近年の傾向を解説します。
人手不足は持続傾向
建築士・住宅設計士は需要が高まっており、人手不足が持続しています。
国土交通省「建築着工統計調査報告」によると、少子高齢化で住宅需要の減少が予想されていた中で、新設住宅着工件数は2013年度から2019年度まで横ばいを維持してきました。中でも貸家(年平均1.1%)や分譲住宅(同0.7%)、一戸建て(同2.4%)は緩やかに増加しており、底堅い需要があることがわかります。
一方、住宅設計関連職の人数はそれほど増えていないのが現状です。例えば、一級建築士の登録者数は2019年4月時点で37.3万人ですが、これは10年前の2009年の33.9万人と比較しても10%しか増加していません。そのため、建築士や住宅設計士の売り手市場は継続しているのです。
なお、2020年は新型コロナウイルスの影響で建築需要が急激に落ち込んでいます。今後はこれまでの売り手市場が転換する可能性もあり、専門スキルの獲得や伸びる分野の見極めといった備えが重要です。
人材を必要とする社会的要因
住宅業界には、建築士や住宅設計士を必要とする背景があります。例えば、高度経済成長期に建築された建物が一斉に老朽化の時期を迎えており、古い建物のメンテナンスや解体工事が必要な状況です。
マンションや商業施設、オフィスビルといった大規模な建物を修繕したり耐震工事を施したりといった需要は増えており、建築士などの専門家が求められています。一戸建てのリフォームであっても、設計や施工管理には専門家が必要です。解体工事の場合も、大型の建築物の場合は監理技術者として一級建築士などの有資格者を設置する必要があります。
顧客ニーズのさらなる多様化も
社会の変化によって、顧客のニーズは多様化している傾向があります。
特に目立つ動きが少子高齢化による高齢者向け住宅のニーズの高まりです。シニアの住民が、自宅を住みやすいようバリアフリーにリフォームして欲しいと依頼するだけではありません。若い顧客の新築案件でも、将来を見据えてバリアフリーを取り入れて欲しいというニーズがあります。
また、環境志向の高まりによって省エネ性能の高い設計にも注目が集まっている状況です。他には、台風や地震、水害などに備えて耐震や防災といった付加価値も求められています。
建築士・住宅設計士のキャリアパス・活躍の場は多様化傾向
建築士や住宅設計士としての働き方はさまざまな種類があり、転職の際は幅広く知っておくと有利です。ここでは主な分野を挙げ、それぞれの特徴を紹介します。
ハウスメーカー
ハウスメーカーは、住宅建築をワンストップで実施する大手住宅メーカーです。自社ブランドを持っていたり、全国展開したりしている大手も多く存在します。
ハウスメーカーの最大の特徴は、営業から施工までの流れが整理され、分業体制が整っている点です。通常は営業、設計、施工などが区分けされていて、設計士として顧客にヒアリングする流れなどもマニュアル化されていることも多いため、仕事を進めやすいという特徴があります。ハウスメーカーは大手も多く、そのような企業では年収が高い傾向があります。
工務店
工務店は、住宅の設計から施工までを一貫して手がける建設会社です。ワンストップという点ではハウスメーカーと同じですが、一般的にはより地域密着型の企業を工務店と呼びます。
工務店では、設計担当者として顧客との打ち合わせから施工、引き渡しまで一貫して携われる点が特徴です。工務店によっては施工業務だけでなく自社設計に力を入れており、その一環として優秀な建築士・設計士を抱えようとすることもあります。携わる業務が広い分、年収も比較的高い傾向があります。
設計事務所
設計事務所は、建物の設計に特化した企業です。ハウスメーカーや工務店は自社内に施工部門も抱えていますが、設計事務所は施工のチェック・管理などをすることはあっても、基本的に自社内に施工部門は抱えません。
設計事務所では、設計に特化している分、意匠性の高い設計や専門性の高い設計に挑戦できる可能性があります。また、建て主と施工会社との間に入り、コストや安全性、施工方法などを巡って調整役を果たすこともあり、建て主のサポート役としての責任は小さくありません。ただ年収に関しては、設計も施工も手がけるハウスメーカーよりもやや劣る傾向があります。
不動産会社
不動産会社は、物件の仕入れや販売・賃貸、物件管理、投資事業などを幅広く手がける企業です。設計ができる人材は、不動産会社において設計以外にもさまざまな働き方が可能です。
例えば、ファシリティマネジメントという、建物を資産として戦略的に活用・管理する仕事があります。建物は耐用年数もあり複雑な構造なため設計者の知見が役立つのです。他には、建設を管理するコンストラクションマネジメントや、その他修繕やメンテナンス案件などを管理するプロジェクトマネジメントといった仕事で活躍する選択肢もあります。
不動産会社では大規模な案件を長期間にわたり担当することもあり、年収は高い傾向があります。
ゼネコン・デベロッパー
ゼネコンやデベロッパーは、設計力、施工技術、案件の規模などが突出しており、建築士・住宅設計士として他とは全く異なる仕事に挑戦することができます。
ゼネコンやデベロッパーの特徴の1つは、手がける物件が特殊なことです。例えば、ゼネコンは超高層建築やドーム球場、発電所といった案件を扱うことがあり、デベロッパーは1,000戸を超える大型マンションや10万平米以上の商業施設など、超大規模物件を手がけることがあります。
設計の難易度は高いですが、設計職としてはトップクラスの収入が見込める点が魅力です。
高収入・キャリアアップにつながる!企業が建築士・住宅設計士に求めるスキル
建築士や住宅設計士の方が転職で高収入やキャリアアップを目指す場合は、どのようなスキルが重宝されるのか知っておくことが大切です。ここでは提案力、設計力、コミュニケーション能力について解説します。
付加価値を高める提案力
付加価値の高い提案ができると企業からの評価は高くなります。これは、価値がある提案ができると、顧客の満足度が高まり、企業の売上が増加する可能性があるためです。
住宅設計の方法は大きく分けて2種類です。まずは定番として、テンプレートや施工パターンがあらかじめ決められており、それに沿って設計を組み立てる方法があります。もう1つは、顧客の希望にもとづいて、なるべくオリジナルの要素も取り入れながら設計を組み立てる方法です。
基本的に前者はパターン化されているので低コストですが、、差別化が難しいため単価競争になりやすいというデメリットがあります。しかし、設計者としてプラスアルファの提案も行えば、顧客に喜ばれるだけでなく、単価も上乗せしやすいのです。
顧客の心を掴む設計力
顧客に響くような設計をする力も必要です。
例えば、住宅設計はハウスメーカー、工務店、設計事務所などあらゆる競合がひしめいています。その中で自社が選ばれるためには、デザインや快適性など、何らかの強みを持っている必要があります。そこで大切なのは顧客にとって価値がある設計を提供できるかどうかであり、そのような設計力がある人材は企業にとっても貴重です。
また、企業は顧客の多様化する要望に対応する必要もあります。そこで、流行もチェックし、バリアフリーや環境性能、防災といったポイントも設計に取り入れられる人材は市場価値が上がるでしょう。
関係者とのコミュニケーション能力
設計職はコミュニケーション能力も重要です。
例えば、住宅設計では顧客の意図を正確に読み取り、設計に要望や思いを丁寧に反映する必要があります。施工段階では施工担当者と完成物のイメージを共有し、食い違いがないように進行しなければなりません。
他にも、マンションやオフィスビルといった大規模な物件を担当する場合は、売主、施工会社、販売会社など関係者も多岐にわたります。設計担当者は、綿密に調整しながら仕事を進めることが求められます。
建築士や住宅設計士としての設計力という専門技術に加えて、関係者とスムーズに連携する能力が高ければ転職では有利です。
建築士・住宅設計士の転職で成功するためのポイントとは?
建築士や住宅設計士の仕事にはさまざまな種類があり、転職で成功するにはスキル・経験の洗い出しや希望の整理が大切です。ここでは転職で成功するための3つのポイントを紹介します。
スキル・経験の棚卸しをする
まずは設計者としてのスキルや経験を棚卸しすることが大切です。
例えば、住宅設計の経験者でも、ハウスメーカーでコスト管理もしながら大量の件数を安定的に設計するスキルを磨いてきたのか、あるいは設計事務所で顧客にじっくり寄り添いながら独自性のある設計を仕上げてきたのかなど、それまでのキャリアによって強みは大きく異なります。
転職で収入増やキャリアアップを狙うなら、自身の得意分野で強みを生かせる職場を選ぶ方が有利です。理想の働き方などを考えるのも大切ですが、転職の際は一度冷静に自己分析してみることが役立ちます。
会社選びの軸を定める
転職先を選ぶ軸を決めることも転職を成功させるために重要です。
一般的に、建築士や住宅設計士の方が仕事で重視する項目としては、収入やキャリアアップなどの他、クリエイティブなスキルを発揮できるか、専門的な技術力を磨けるかといった要素があります。そして、何を重視するかによって、以下のように最適な選択肢は全く異なるものです。
・年収を高めたい→大手ハウスメーカー
・キャリアアップしたい→ハウスメーカー、工務店、設計事務所
・意匠性を重視したい→アトリエ系設計事務所
・専門性を磨きたい→不動産会社
転職エージェントに相談する
転職エージェントを活用することも成功の可能性を高めます。
建築士や住宅設計士としてのキャリアが長ければ、豊富な経験の中で多様なスキルを身につけているものです。そのような中、転職先から評価される自分の強みは何なのか、より活躍できる分野があるのかを客観的に分析することは簡単ではありません。また、数ある求人の中から自分に合う案件を選び出すのにも時間や労力が必要です。
転職エージェントは、カウンセリングを通して、設計職としてのこれまでの経験やこれからの希望をヒアリングし、強みや優先順位の洗い出しをサポートします。その上で、非公開を含む優良な求人の中から最適な案件を提案。面談の調整や条件交渉まで依頼できるので、転職の成功につながりやすいのです。
【サービス紹介】『転機』ではこれまでのご経験を活かせる、新たなキャリアの提供が可能です
ハイクラス・エグゼクティブの移籍を専門に手掛ける『転機』では、建築士や住宅設計士をはじめ、第一線でご活躍中の方やご経験をお持ちの方に、その知見やノウハウ、卓越したリーダーシップや推進力を活かせる新たなキャリアをご提供します。
・経験豊富なコンサルタントによるキャリア支援
・経営幹部ポジションで年収1,000万円以上といった移籍先のご紹介
・移籍先候補企業の経営者と、直接面談が可能
『転機』では優良な非公開案件を多数抱えており、会員者様には1人ひとりのキャリアや志向をもとに、ご経験を活かせる新たな移籍先を個別にご提案させていただきます。
ご興味をお持ちいただければ、会員登録(無料)をお願いいたします。ご経歴・ご経験に相応しい案件をご紹介いたします。
※すべての方に求人をご紹介できるサービスではございません。あしからずご了承のほどお願いいたします。
建築士・住宅設計士の仕事内容
建築士や住宅設計士は、設計のプロとして顧客へのヒアリングや要望書などをもとに設計を行います。建築士は「一級建築士」などの国家資格を保有している人物を指し、住宅設計士は資格を必要としない領域や建築士の補助業務を担当するという違いがあります。
建築士などの設計職は、設計業務だけでなく、顧客との打ち合わせ、施工部門との調整、施工のチェックなど、注文から引き渡しまで幅広く携わることもあります。
建築士・住宅設計士のやりがい
建築士や住宅設計士は、自身が設計に携わったものが、多くの人の手によって最終的に形になるという魅力があります。顧客へのヒアリングを重ね、コストや納期といった制約の中で設計し、施工にも関わるなど責任は重大ですが、住宅やオフィスビルといった多くの人の生活・仕事に関わる資産を手がけられることは設計職特有の魅力です。
会員登録
会員様のご経歴に応じて、特別案件としてお知らせしております。
※会員登録は無料です。